お花見に欠かせない「花見団子」由来や3色の意味は?手作りレシピも

「花見団子」は、花見の季節に欠かせない甘味の一つですよね。
串に刺さった赤、白、緑の3色団子を見ると春を感じる、という人も少なくないはず。
今回は、春に人気の和菓子「花見団子」について、歴史やレシピなど詳しくご紹介します。
「花見団子」はなぜ食べる?
昔から日本で親しまれてきた花見団子ですが、そもそもいつごろから食べられているものなのでしょうか。
まずは、花見団子の歴史や意味について解説します。
歴史
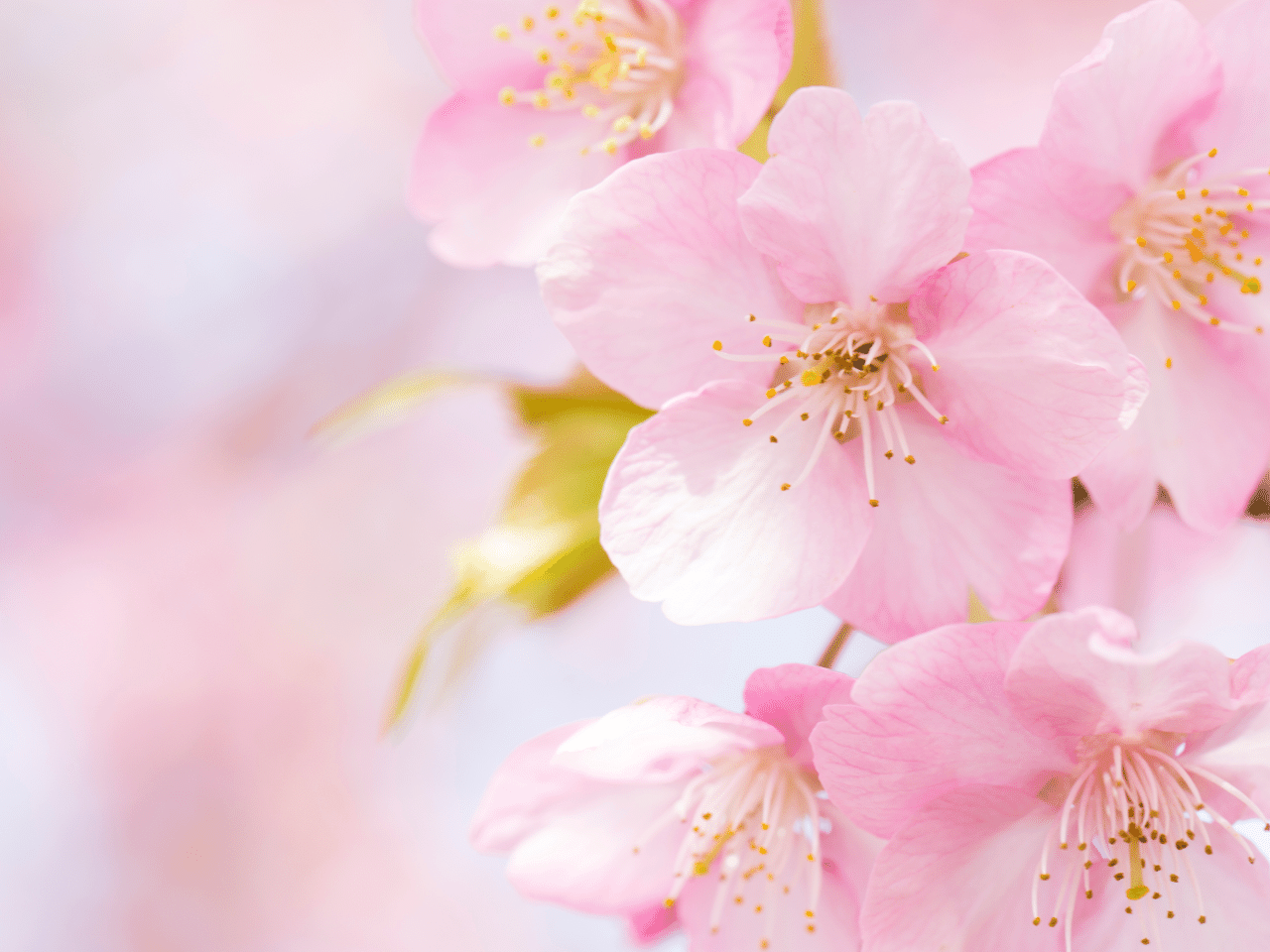
花を見ながら食事を楽しむ現代の花見スタイルは、豊臣秀吉が由来だと言われています。
桜の木がたくさん移植された場所で酒宴を開き、日本各地の甘味を集めて食べたことが花見の始まりです。
このときに招待客に振る舞われたのが、色鮮やかな花見団子だったとされています。
江戸時代中ごろになると、桜を見ながら花見団子を楽しむ風習が庶民にも広く受け入れられ、日本国内に浸透しました。
3色「赤」「白」「緑」の意味

団子の3色については諸説ありますが、赤は「桜」、白は桃の節句に飲むお酒「白酒」、緑は「よもぎ」や「新緑」を表しているとされています。
また、赤は春、白は冬、緑は夏と、それぞれの色が四季をイメージしているという説も。
秋が含まれていないのは、「秋がない」と「食べても飽きない」をかけているそうです。
3色の花見団子が一般的ですが、地域や和菓子店などによっては4色の花見団子も存在しますよ。
順番にも意味がある
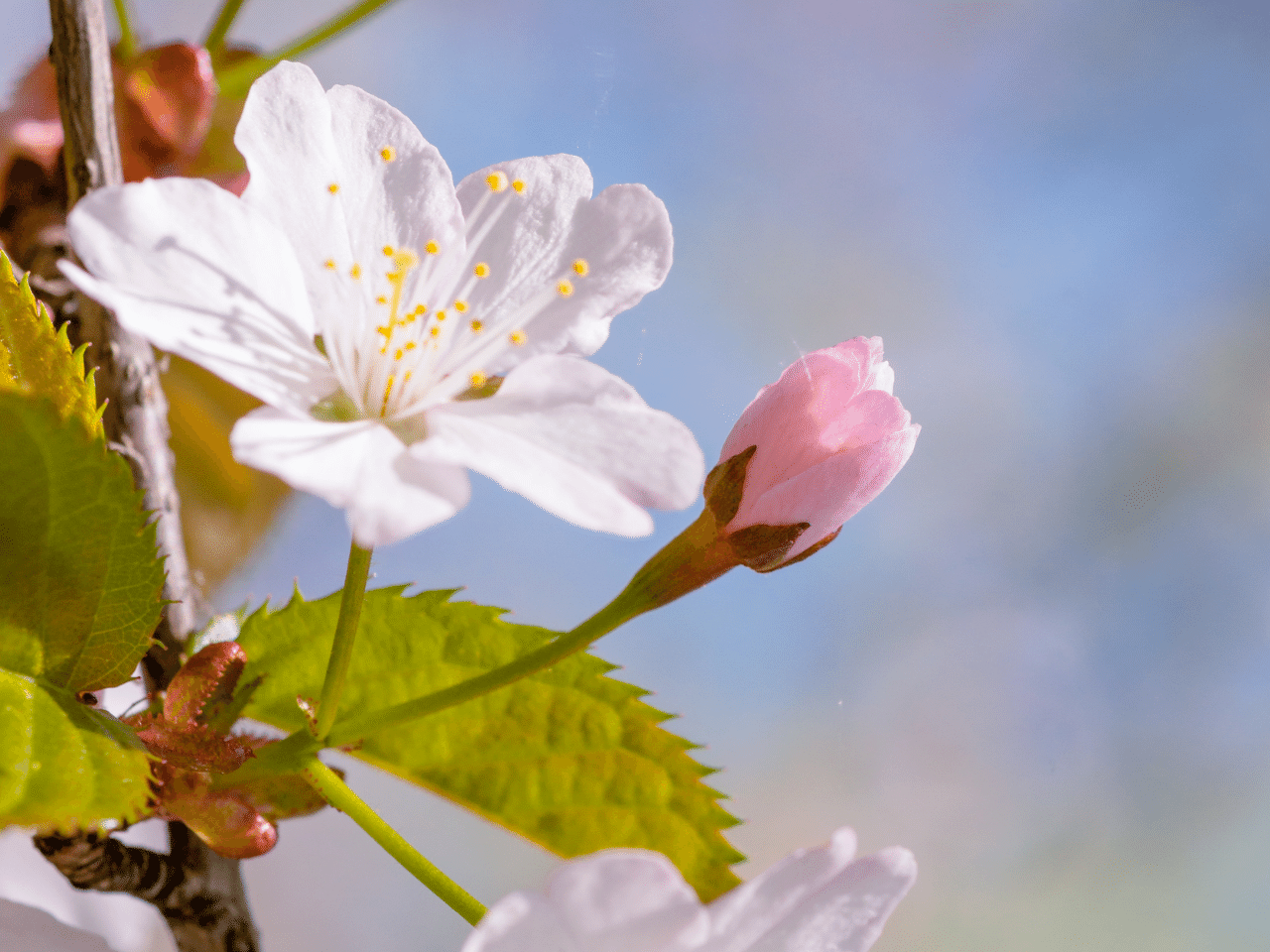
花見団子は、上から赤、白、緑という順番に串に刺さっていることが多いですよね。
これは、赤いつぼみがついた後、白い花が咲き誇り、花が散ると緑の葉が成長するという、桜の木の変化を表現していると言われています。
そのほか、雪解けの様子を表しているともいわれており、赤は太陽、白は地面に残る雪、緑は雪の下に芽吹く新緑を意味するとされる説も残っています。
お花見に持っていきたい「花見団子」レシピ
ここからは、お花見に持っていきたい「花見団子」のレシピを紹介します。
作り方も簡単で材料も揃えやすいので、気になるレシピがあれば、ぜひ一度作ってみてくださいね。
上新粉でつくる「花見団子」

■材料
上新粉...220g
上白糖...40g
熱湯...150ml
抹茶パウダー...適量
食紅...適量
上新粉、上白糖、熱湯を混ぜ合わせ、3等分にします。
1つには抹茶パウダー、1つには食紅を加えて、さらに混ぜてください。
3つに分けたそれぞれの生地を一口大に丸めます。
丸めた団子を鍋に入れて5分間茹でたら、冷水に入れてぬめりを取りましょう。 団子の水気を切って、串に刺したら完成です。
モチモチ食感「白玉粉と豆腐の花見団子」

■材料
白玉粉...120g
豆腐...120g
砂糖...大さじ3
食紅...適量
抹茶パウダー...適量
白玉粉と豆腐をこねて3等分にします。
1つは食紅、もう1つは抹茶パウダーを入れて混ぜ合わせます。残りの1つは何も混ぜずにそのまま使います。
耳たぶくらいの固さになったら、一口大に丸めて、沸騰したお湯で2分程度茹でましょう。
水に入れて粗熱を取り、串に刺したら花見団子の出来上がりです。
レンジで簡単「花見団子」

■材料
上新粉...100g
水...150ml
砂糖...大さじ3
乾燥よもぎ...2g
食紅...適量
上新粉と水、砂糖を混ぜ、ラップをかけて600Wで3分間ほど温めます。
1度取り出してヘラで混ぜたら、再度レンジで1分温めて混ぜるという作業を2回繰り返しましょう。
生地が透明になったら3等分に分け、1つは食紅を溶いた水で色をつけ、1つは熱湯でふやかした乾燥よもぎを入れます。
最後に3種類の生地を一口サイズに丸めたら完成です。
団子を丸めるときは、水と砂糖をレンジで溶かしたシロップを手につけると、団子を丸めやすいですよ。
野菜で色付け「花見団子」

■材料
白玉粉...100g
絹豆腐...100g
砂糖...大さじ2杯
ほうれん草...1株
にんじん...20g
ほうれん草を下茹でしたら、根の部分を切り落としてからみじん切りにします。
にんじんは皮をむいて、すりおろしておきましょう。
白玉粉と豆腐、砂糖をゴムベラで混ぜ、ある程度まとまってきたら手でこねます。
こねた生地を3等分に分け、1つはほうれん草、1つはにんじんを加えましょう。
耳たぶの固さくらいになるまでこねたら、一口大サイズに丸めます。
鍋にお湯を沸かし2〜3分ほど茹でたら、冷水に入れて冷やしましょう。水気を切り、最後に串に刺せば完成です。
「花見団子」を食べて、春の訪れをお祝いしよう!

春らしい鮮やかな色の「花見団子」は、比較的簡単に作れます。
今回ご紹介したレシピを参考に、ぜひ手作りしてみてはいかがでしょうか。
手作り団子で花見をすれば、いつもより深く春を感じられるかもしれませんよ。
